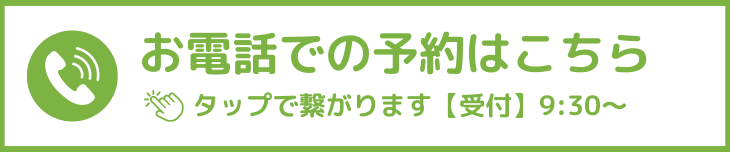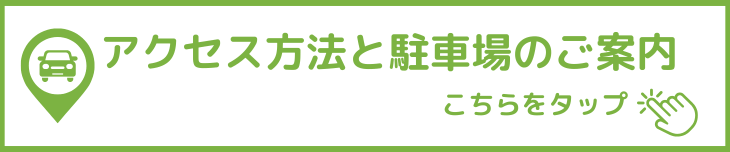くるぶしの下に痛みを抱えている人の多くに足アーチの問題が潜んでいます。
こちらの記事では、くるぶしの下が痛くなるメカニズムについて解説していきます。くるぶし付近の痛みが治らない方は内容をご参考ください。
外くるぶしや内くるぶしが痛くなる理由
足のアーチは身体を支えるのに重要な役割を果たしていますが、多くの人が本来のポジションにおさまっておらず、機能不全を抱えています。
スポーツのクセや不適切な靴を履いて生活をするなど、普段の習慣によって崩れやすく、足アーチが低下しているケースがよくみられます。
アーチには、内側縦アーチ、外側縦アーチ、横アーチがあり、骨、靭帯、筋で構成されます。
足アーチが低下することで、一部の骨や筋肉に負担がかかり、くるぶし付近に痛みを発生させることになります。くるぶしの痛みを改善するためには足アーチの修正が最も重要なポイントといえます。
足アーチを保持する筋肉は以下の通りです。
長腓骨筋の緊張
長腓骨筋は、腓骨の骨頭、外側面から付着し、外果(外くるぶし)を通り、足の裏を超えて、足根骨の裏に付着している筋肉です。
このように繋がることで、足先の底屈や外反させることが可能になり、歩く、走る、登るといった動作を安定させます。
長腓骨筋は、使用される頻度が多い筋肉であり、疲労を起こしやすい筋肉です。長腓骨筋に問題が起きると、足首の外側に痛みを発生させます。(関節炎の徴候や腱炎と誤診されやすい)
歩く、走る、登るなどの動作を過度に行う、ヒールを履く、脚を組んで座るといった習慣は、長腓骨筋に過剰な負荷を与えることになります。
後脛骨筋の弱化
後脛骨筋はふくらはぎの下に位置し、脛骨と腓骨、そして両方をつなぐ骨膜間に付着しています。足の底屈を助け、足アーチを維持し、体重を適正に足の外側にかける働きがあります。
不安定な道を歩いたり、走ったりすると後脛骨筋にストレスがかかります。靴が足に合っていない場合にも同様です。
モートン病の場合では足の内側を使って歩くので、後脛骨筋を過剰に働かせてしまい、くるぶし周囲に痛みがでやすくなります。
後脛骨筋が衰えてくると(PTTD)、膝が内側に入りやすく、足アーチが落ちてきます。内果(内くるぶし)下方に腫張や痛みが見られ、やがて偏平足が現れます。
前脛骨筋の弱化
前脛骨筋は、脛骨の上部から前面に付着していて、腱は足の甲を縦断し、足を巻き込むようにして足底の骨に付着しています。
前脛骨筋がこのように付着していることで、足の背屈や内反動作が可能になります。また、内側縦アーチを保持する筋肉のひとつです。
前脛骨筋は、歩く、走る、登る動作で負荷がかかることがあります。長時間の車の運転も同様に筋肉を疲労させます。
前脛骨筋の疲労で筋力低下が起きると、つま先が下がり、地面や階段でつまずきやすくなります。
まとめ
くるぶしの痛みは、足アーチの問題を修正することで解決できる可能性が高いです。特に弱くなりやすい後脛骨筋にアプローチすることが改善のポイントになります。
当院では、優しいアプローチによって緊張状態にある身体を深部から緩めていきます。痛みを感じることはないので、ご高齢の方や妊婦の方も安心して施術を受けることができます。